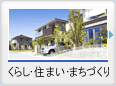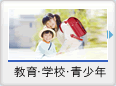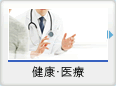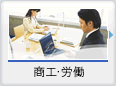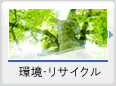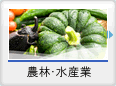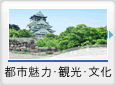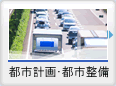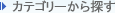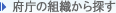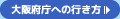生活保護とは
私たちは、誰でもその人生において、病気、けが、障がい、離婚、失業、高(加)齢など様々な事情により収入や貯蓄がなくなり、生活に困ることがあります。生活保護制度はそのような時に、国民の権利として認められている、日本国憲法第25条の『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するものです。また、再び自分たちの力で生活していくことができるように、『自立を助長(支援)すること』をその目的にしています。
生活保護を受けるには
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
本人、同居の親族、扶養義務者であれば、必要な書類が揃っていなくても相談、申請することができます。
相談の窓口
町村(島本町を除く)にお住まいの方は、大阪府の子ども家庭センター(箕面、貝塚、富田林)にご相談ください。
市区町にお住まいの方は、各市区町の福祉事務所へご相談下さい。
各市区町の福祉事務所及び子ども家庭センターへの連絡先はこちら⇒府内福祉事務所一覧
申請手続き
生活保護を受けるには申請が必要です。
申請は、お住まいの市区町村を所管する福祉事務所及び子ども家庭センターで行ってください。
申請に必要な書類は、福祉事務所及び子ども家庭センターにあります。
申請できる方は、本人、扶養義務者、同居している親族のいずれかです。
申請に関する詳しい内容についてはこちら⇒生活保護の申請手続き [Wordファイル/77KB]
どのような方が生活保護を受けられるか
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。また、扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先されます。以下のような状態の方が、最低生活が維持できない場合に保護を受給することができます。
- 働くことができない、又は働いていても必要な生活費を得られない。
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、直ちに現金化して活用することができる資産がない。
- 年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない。
生活保護の要件にあてはまらないが、生活にお悩みの方の相談窓口として生活困窮者自立支援相談支援機関が各市町にあります。経済的な問題や就労などの相談をお受けしています。
資産の活用とは
活用できる資産は売却・解約等により活用し、生活費に充ててください。
- 資産とは、土地・家屋などの不動産、預貯金、有価証券、生命保険、自動車、貴金属等を指します。
- 最低生活維持のために使用・貸借等され、自立助長に役立つ場合、保有を認められることもあります。
- また資産がある場合であっても直ちに活用(現金化)できない事情があるときは、その資産が活用可能となった場合、支給した生活保護費の範囲内で費用を返還することを条件に生活保護が適用となる場合があります。(生活保護法第63条)
- 詳しくは申請時に各市区長の福祉事務所又は子ども家庭センターの窓口にてご相談ください。
能力の活用とは
働くことができる人は、その能力に応じて働いて収入を得てください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当、保険など、他の制度が活用できる場合は、そちらをまず利用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、親族等からの援助が生活保護に優先されます。
- ただし、親族等からの援助は生活保護の要件ではありませんので、生活保護を受けられるかどうかの判定には影響しません。
- 「扶養義務の履行が期待できない」と判断される親族等には、基本的には直接書面等で援助の可否を調査しない取扱いとされています。
生活保護の仕組み
厚生労働大臣の定める基準(最低生活費)によって計算された、世帯の最低生活費とあなたの世帯の収入とをくらべて、収入の方が少ないとき、その足りない分が保護費として支給されます。
保護が受けられる場合
収入が最低生活費を下回る場合、その不足分のみ保護が受けられます。
最低生活費(最低生活保障水準) | |
収入(就労、年金等) | 保護費 |
保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回る場合、保護は受けられません。
最低生活費(最低生活保障水準) |
収入(就労、年金等) |
最低生活費とは
国(厚生労働省)が定めた基準に基づいて計算された、あなたの世帯の最低生活の維持に必要な費用のことです。生活費、住宅費、教育費等現金で支給される費用だけでなく、医療や介護など、福祉事務所又は子ども家庭センターから直接医療機関などに支払われる費用(サービス支給)も含みます。
収入とは
働いて得た収入、受給している年金や手当、保険の給付金、仕送りなど、あなたの世帯に入るすべての収入の合計のことです。借入金も収入とみなします。なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料等の実費控除の他、収入に応じて一定の控除がなされます。
生活保護の種類
生活保護は次の種類の扶助から構成されます。
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費等、日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費、給食費等 |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅補修費等に必要な費用 |
医療扶助 | 病気の治療等で医療機関にかかるための費用、薬代等 |
介護扶助 | 介護サービスを利用するために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 就職に必要な技能を身につけるために必要な費用、高等学校に就学するために必要な費用等 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用(被保護者が喪主の場合に支給されます。) |
- ひとり親世帯や障がい者世帯など、世帯や世帯員の状況に応じて、生活扶助費に各種加算額が計上される場合があります。
- 紙おむつ代や通院交通費なども支給される場合がありますので、事前に各市区長の福祉事務所又は子ども家庭センターへご相談ください。
- 医療扶助や介護扶助については、必要な費用を、各市区長の福祉事務所又は子ども家庭センターから医療機関や介護サービス事業者などに直接支払います。
生活保護制度以外の支援制度等
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護審査・指導グループ
ここまで本文です。

 府庁の組織から探す
府庁の組織から探す