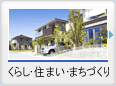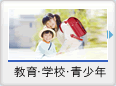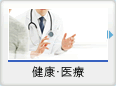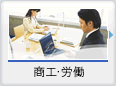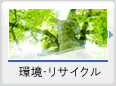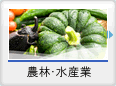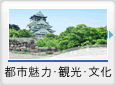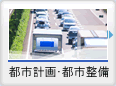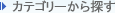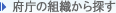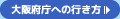更新日:2016年9月1日
コースです。
| 写真1 南海ウイングバスの終点「塔原(とのはら)」バス停がスタート地点です。 公衆トイレもあります。 | |
| 写真2 バス停からしばらくは旧本谷林道を進みます。 | |
| 写真3 途中、路案内の看板があります。 |  |
写真4 | |
| 写真5 バス停から10分ほど歩くと、右手葛城山を示す道標が現れます。 | |
| 写真6 ここで右折して下さい。 ※直進すると旧本谷林道を進んでしまいます。 |  |
| 写真7 しばらく急な上り坂が続きます。 | |
| 写真8 山頂までの距離を示す石柱が道しるべに。 山頂まで3,200m | |
| 写真9 上り坂で少ししんどいですが、木漏れ日が爽やかです。 | |
写真10 | |
| 写真11 右折して下さい。 |  |
| 写真12 山頂まで2,600m。 | |
| 写真13 しばらく歩くと枇杷平(びわだいら)に出ます。 | |
| 写真14 「献燈」とあります。 | |
| 写真15 少し古くに設置された「丁石」もあります。 1丁は約109mで、山頂までの距離をあらわします。枇杷平から山頂まで約2,200m。 | |
| 写真16 枇杷平から少しだけ貝塚方面の景色が望めます。 | |
| 写真17 少しだけ歩きやすい道になってきました。 | |
| 写真18 バイク止めを抜けると本谷林道に出ます。 | |
| 写真19 本谷林道を斜めに横断します。 山頂まで2,000m。 |  |
| 写真20 ちょっとだけ階段を上がります。 | |
| 写真21 人工林の中を進みます。 | |
| 写真22 再び、右手に本谷林道が見えてきます。 | |
| 写真23 再び、本谷林道と合流。 しばらく本谷林道を歩きます。 | |
| 写真24 山頂まで1,800m | |
| 写真25 途中、左手に岸和田側に展望が開けます。 | |
| 写真26 本谷林道を300mほどすすむと分岐点が見えてきます。 右方向に進んでください。 |  |
| 写真27 ブナ林に近づいて来ました。 ここから山頂まで約1,400m | |
| 写真28 和泉葛城山ブナ林は大阪みどりの百選にも選ばれてます。 | |
| 写真29 広葉樹林と人工林の入り混じった中を進みます。 途中、玉冷泉の石柱がありました。 | |
| 写真30 分かりにくいですが、ここからしばらくはブナ林の緩衝地区「バッファーゾーン」に入ります。 | |
| 写真31 バッファーゾーンでは、ブナ林の保全活動として、山頂周辺で採取した種子を育てたブナの苗木を植栽してます。 | |
| 写真32 山頂まで400mのところまできました。 蒸し暑さが無くなり、とても快適です。 | |
写真33 | |
| 写真34 コアゾーンに入ってすぐ左手に観察デッキが見えてきます。 | |
| 写真35 観察デッキでちょっと休憩。 | |
| 写真36 正面にはブナ林が広がります。 | |
| 写真37 登山道にもどり山頂を目指します。ところどころにブナの大木が見えます。 | |
| 写真38 ハイキングコースが交差する十字路にでます。正面の山頂に続く高龗(たかおがみ)神社への石段を登ります。 | |
| 写真39 この先を進めば山頂です。 | |
| 写真40 標高858mの和泉葛城山に到着。 大阪側には石の宝殿がある高龗神社があります。 | |
| 写真41 ブナは本来、標高が高くて涼しい気候の地域に生息します。 和泉葛城山ブナ林は本州生息域の南限に近く、比較的標高の低い地域に天然のまま残っている貴重な植物層として、大正12年(1923年)に国の天然記念物に指定されました。 | |
写真42 | |
| 写真43 背面の右側角に注目。 | |
| 写真44 角が切り落とされてます。 これは、領地を侵犯しているとして設置後に削らされたとか・・・ その昔、紀州勢力がいかに強かったか、の語り草です。 | |
| 写真45 背中合わせになる和歌山県側には龍王神社があります。 | |
| 写真46 竜王神社の正面。 | |
| 写真47 この山頂辺りに、葛城二十八経塚のひとつ「授学無学人記品」第九経塚があったとされています。 | |
| 写真48 龍王神社の右手には石仏や・・・ | |
| 写真49 木札が納められています。 | |
| 写真50 山頂周辺にもブナの大木がちらほら。 | |
| 写真51 山頂を抜け和歌山県側の参道を抜けます。 | |
| 写真52 参道を抜けると紀泉高原(スカイライン)にでます。 | |
| 写真53 紀泉高原には四阿や広場があります。 ※昔あった茶店は閉店してます | |
| 写真54 四阿から紀の川が眺望できます。 | |
| 写真55 山頂から100mほど東に展望台もあります。 | |
| 写真56 展望台からは大阪湾が望めます。 | |
| 写真57 公衆トイレは駐車場の奥にあります。 | |
| 写真58 帰りは一旦、牛滝林道側に出て、通称「ブナ街道」を抜けて貝塚市側に出ることにします。 | |
写真59 | |
写真60 | |
| 写真61 ブナの木は葉に葉脈の先端箇所に特徴がありますが、幹にも独特の模様があります。 | |
| 写真62 ブナ街道を抜け十字路(写真38と同じ地点)に戻ってきました。 この先は通称Bコースといわれる貝塚市蕎原(そぶら)に至るルートを進みます。 ※右側の路が往路(岸和田市塔原方面)になります |  |
| 写真63 貝塚側にも多くのブナの大木があります。 | |
| 写真64 ブナの根を踏まないよう所々に木道がついています。 | |
| 写真65 看板が見えてきたらコアゾーンは終了。この先はバッファーゾーンになります。 | |
| 写真66 雑木林の中を下山します。 | |
写真67 |  |
写真68 | |
| 写真69 再び沢筋を渡ります。 |  |
| 写真70 途中、路面が荒れてますので足元に注意して歩いて下さい。 | |
| 写真71 だんだん渓流らしくなってきました。 | |
| 写真72 右手にはハシカケノ滝(白糸滝)が見えます。 | |
| 写真73 ここからしばらくは、渓流に沿って歩きます。 | |
| 写真74 左手にブナの植栽地が見えてきました。この辺りでバッファーゾーンは終了です。 | |
写真75 | |
| 写真76 途中、T字路を右折します。 |  |
| 写真77 渓流の水がとても綺麗です。 沢山の小魚が泳いでいるのが見えます。 | |
| 写真78 区画整理された駐車場(有料)が見えてきます。 | |
| 写真79 東手川(とてがわ)林道に出ますので右折して下さい。 |  |
| 写真80 春日橋を渡ります。 この橋より下は市道になります。 | |
| 写真81 左手に公衆トイレが現れます。 | |
| 写真82 この辺りは「蕎原渓流園地」です。 夏休みシーズンはバーバーキューや川遊びなどで賑わいます。 | |
| 写真83 市道を下る途中、左手に広場や建物が見えてきます。 | |
| 写真84 「そぶら山荘愛(まな)のパン」です。 | |
写真85 | |
| 写真86 フル回転の釜 | |
| 写真87 渓流の対岸にも行け、広場や簡単な遊具があります。 | |
| 写真88 そぶら山荘を出て市道を下ります。 この辺りではシイタケ栽培が盛んです。 | |
| 写真89 蕎原の集落に出ます。 | |
| 写真90 信号のある交差点を右折します。 左折したところには、バス停があります。 |  |
| 写真91 はーもにーばすの「蕎原(そぶら)」バス停です。 |  |
| 写真92 交差点を右折したら、ゴール地点となる塔原バス停まで車道を歩きます。 | |
| 写真93 クルマに注意して歩いて下さい。 | |
| 写真94 途中、右手に箱谷林道の入口が見えてきます。 | |
| 写真95 この箱谷林道からも、枇杷平を抜けて葛城山頂へ至ることができます。 | |
| 写真96 すぐ近くには、箱谷林道を歩くときに便利な駐車場(有料)もあります。 | |
| 写真97 駐車場内には公衆トイレも整備されています。 | |
| 写真98 塔原の集落に出ます。 左折すると「塔原口」バス停が近くにありますが、今回はスタート地点の「塔原」バス停まで戻ります。 |  |
| 写真99 距離にして200mほどです。 |  |
| 写真100 ゴール地点となる「塔原」バス停に戻ってきました。 公衆トイレがありますので、バスを待つ間に簡単な身支度もできます。 ここまでの所要時間は約4時間30分(休憩時間抜き)です。 | |
| 写真101 【番外編】近隣スポットの紹介 ほの字の里 蕎原小学校の跡地を利用した宿泊施設です。天然温泉のかいづか温泉ほのぼの湯や日曜市が魅力。 | |
| 写真102 【番外編】近隣スポットの紹介 相川町のホタル 川沿いに散策用歩道が整備されシーズンには多くの方が観賞に訪れます。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 総務・自然公園グループ
ここまで本文です。

 府庁の組織から探す
府庁の組織から探す